
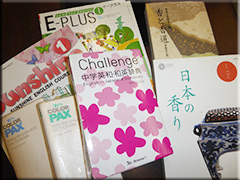
この数年、外国人の診療や国際学会のために英会話を勉強しており、また昨年、セミナーで香道を実施して以来、香り用語というものに興味を持ち始めました。そこで今回は 英語と日本語の香りに関する語の微妙なニュアンスの差異について考えてみます。
まず英語ですが、匂い、香りを表す英単語と和訳としてはSmell:嗅覚・におい・香り・悪臭、Odor:におい・香り、Odorant :有臭物質、Perfume:香り・芳香・香料・香水、Fragrance:芳香・かぐわしさ、Aroma:芳香・気品、Incense:香・芳香、flavor:味、風味、味わい、趣、などがあり、同様な形容が多いのが目立ちます。
一方、和語ですが、“におい”の筆記だけでもにおい、ニオイ、匂い、臭いと4つもあります。香り和語としては芳香:かぐわしい様、香気:よい香り、香味:においと味わい、などがあります。セミナーでお世話になった堀之内夕子先生により専門的な和語を御解釈頂いたところ、
- 馥郁(ふくいく)
- 鼻腔や身体全体に染み渡るような、吸い込んで深く味わいたくなるような、辺りにも自身にも漂うふくよかな円やかなる香り。
- 佳香(かこう よきか)
- 梅花など甘く柔らかく漂うさま。
- 佳芳(かほう)
- 佳香と同様に“よきにほひ”ではあるが、麝香を希釈した程度のやや強めな芳しいさま。
- 芳“醇”(ほうじゅん)
- 香り高い味わいやその様子が大変見ごたえがあることであり、混じりが無く滑らかでふくよかなさま。
- 芳“純”(ほうじゅん)
- 清らかで透明感がある人柄やさまを表し、日本人的、日本的な香りに使われることが多い。
などと独自の世界観でお答え頂きました。他には余香、残り香、余薫、献香などまだまだ数多く存在します。ちなみに馥郁の英訳は、なんとこのコラム名である「Sweet-Smelling」で、実は今まで知りませんでした。英語の方が一見、エレガントに見えますが、やはり和語の方が日本古来の歴史と文化を背景とした繊細かつ奥深さが垣間見られると思います。

5月に広島での日本耳鼻咽喉科学会に参加しました。懸案であった嗅覚障害に対して行う、無作為に物のにおいを嗅ぐ自己治療法の名称がほぼ決まったようです。この欄ではまだ記載は控えますが、嗅覚トレーニング、嗅覚リハビリテーションなどよりも治療の一環を位置づけるいいネーミングだと思いました。
今回は広島冷麺、広島焼きを食べました。生牡蠣に対して焼き牡蠣はあまり好きではなかったのですが今回お好み焼きとして食べると意外に美味しかったです。牡蠣はプランクトンを主食としており、そのプランクトンにはジメチルプロピオテチンが含まれています。それが牡蠣の体内で変化してジメチルスルフィドという香り成分に変化することにより、牡蠣独特の匂いとなります。次回訪れた際には日本の「香り100選」の厳島神社潮の香りと、シトラスパーク瀬戸田の柑橘類の香りを嗅ぎ楽しみたいです。
