第29回 平成23年1月20日(木)14:00〜16:00
▼二宮るみ先生(左)

▼バスフィズ

▼月桃ハーブティー
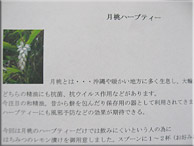
■■ 第13回日本アロマセラピー学会(H22/11月大阪) ■■
参加報告:当院院長
- 特別講演香り感覚の最先端科学:嗅覚の特性を説明する分子機構
- 倉橋 隆(大阪大学生命機能研究科ダイナミクス講座)
- ニオイ分子が嗅繊毛の受容体に受容されると、細胞内にCaイオンが流入し、電気信号となり脳に伝わり、においを認識する。
→同じにおいが続くとCaイオンがカルモデュリンという蛋白と結合しイオンの流入が阻害されるため、においが判らなくなる(これを嗅覚疲労という)ということを追加説明しました。 - シンポジウム沖縄産ゲットウ(月桃)精油の成分分析及び抗不安作用
- 村上 志緒(グリーンフラスコ研究所)
- ショウガ科で学名はAlpinia zerumbet。 葉油(ようゆ)であり、主な香り成分はp-cymene、terpinen-4-olなど。マウスに対しての高架式十字迷路試験にてこれら成分吸入後はオープンアームへの滞在時間が有意に増加することより、月桃が抗不安作用を呈する可能性が示唆された。
→アロマスクール月桃は鹿児島でも生育するので馴染み深かったことが店名の由来だそうです。 - 一般演題芳香療法が有効であったアルツハイマー型認知症(第3期)の一症例
- 春田博之(医療法人春田クリニック)
- ローズマリーとレモンのブレンド精油を毎朝患者の胸元のティッシュに2滴滴下したところ、身動きとれなかった患者が1Wで寝返りを打ち、1ヶ月で笑うようになった。
→その裏づけとなる論文として「高度アルツハイマー病患者に対するアロマセラピーの有用性」(鳥取大学生体制御学 神保太樹 アロマセラピー学会誌vol.7 No1)を紹介しました。 - 一般演題鼻アレルギーにおける蒸気吸入(ティートゥリー)の有用性(第2報)
- 当院院長
- 妊娠・授乳患者30名を精製水群12名と精製水+ティートゥリー群18名とに分け、鼻アレルギー日誌に基づくSymptom Scoreで統計学的に比較検討したところ、両者に有意差を認めた。
→ティートゥリーと比較する意味で今回はペパーミントの蒸気吸入も参加者に試してもらいました。
■■ バスフィズ(入浴発泡剤) ■■
アロマスクール月桃:二宮るみ先生
紙コップに重曹30g、クエン酸10g、バスオイル10mlとマンダリン5滴、リトセア3滴、ラベンサラ2滴を加えよくかき混ぜた後、ラップを敷いて指でよく押し固めて完成。
■■ 月桃ハーブティー ■■
アロマスクール月桃:二宮るみ先生
もう少しハーバルなニオイかと心配していましたが、思ったより飲みやすかったです。セイロンティーに似ているでしょうか。月桃の精油の方も嗅いでみたいものです。
